『保守論壇亡国論』の「中西輝政批判」の一部です。「書くことの内的必然性」の欠落。保守論壇の劣化とは何か。保守論壇は、何故、かくも幼稚になったのか? 『保守論壇亡国論』は、左翼思想を根拠に、単純に保守や保守論壇を批判し、否定するもではない。保守思想の活性化、再生を模索するものである。
新刊『保守論壇亡国論』予約発売開始!!!
(9/16書店発売)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4906674526?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&lc
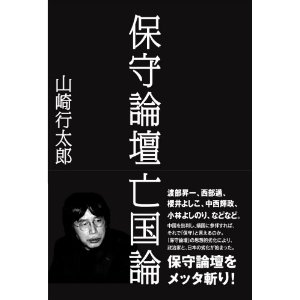
■中西輝政にとっての「保守」とは
保守論壇や保守系ジャーナリズムにおいて、中西輝政という政治学者・政治評論家は無視できない存在である。中西は『正論』や『諸君!』(休刊)、『Voice』などの保守系オピニオン誌の常連寄稿者で、政治評論や政治分析を次々に発表する一方で、自民党を中心とした保守政治家たちに接近し、政策の立案から実行に至るまで深く関わり、かなりの影響力を持っているように見える。
特に第一次安倍政権時代は、「安倍総理のブレーン五人組」が騒がれたが、その時も、その中心的な人物として中西の名前が挙がっていた。中西は安倍晋三と組んで、自分の考えた政策を立案し、「強い日本」の復活を目指すつもりだったのかもしれない。中西自身はこのことを否定しているが、政界に強い影響力を持っていたことは事実だろう。
第一次安倍政権時代の、教育基本法改正や憲法改正関連の法案など、「新保守革命」に相応しい様々な改革の実行には、中西の思想的影響が見られる。それらの試みは、安倍総理の早期退陣で、志半ばで挫折することになったが、いずれにしろ中西が、かなり行動的な人間であり、政界や政局に深く関与することを躊躇しない政治思想家であることは間違いない。
あるいは中西は、第二次世界大戦下に、海軍の高木惣吉などとの関係から積極的に政治や軍事に介入しようとした西田幾多郎や高山岩男、高坂正顕など、かつての京都学派の哲学者たちのことを念頭に置いていたのかもしれない。
しかし、私は、中西が京都学派の哲学者たちと同じような「歴史的使命感」や「書くことの内的必然性」を自覚しているかどうかという点になると、疑問を感じざるを得ない。中西の言論活動は、その意欲的な戦略的言説の割には影が薄い。それはおそらく中西の説く政治思想が陳腐であり、その政治戦略にしても、誰でも思いつきそうなものにすぎないからだろう。
中西は、高坂正堯や江藤淳から強い影響を受けて保守になったという。しかし、私には、中西が、高坂や江藤のラディカルな政治思想を継承しているようには見えない。中西の政治評論は平凡で通俗的であり、高坂や江藤が持っていたような思考の「鋭さ」や「深み」はない。そのため、中西には、高坂の『宰相吉田茂』や江藤の『夏目漱石』のような、この人にしか書けないというような「作品」がない。
中西は果して、保守や保守思想家の名に値する存在なのか。中西は八木秀次との対談で、こう言っている。《私にとっての保守というのは、やはり「生活感覚」というか、思想ではないんですね。(中略)大学に行って、当時流行していた現実主義の代表的論客である高坂正堯先生のもとで国際政治を学びました。それは世界情勢を知る上でとても勉強にはなりましたが、保守への決定的目覚めとまでは言えません。
やはり私にとってコペルニクス的転回と言えるほど決定的だったのは、二十五、六歳の頃から数年、イギリスのケンブリッジ大学で学んだことでした。》(『保守はいま何をすべきか』)ここから、中西の「保守」の中身が想像できる。中西の「保守」は知識なのだ。
そもそも、中西は本当に高坂正堯や江藤淳を読んでいたのだろうか。中西の出身校である京都大学は、当時、左翼学生運動の中心地の一つだったはずである。
私は中西とほぼ同世代で、大学時代に高坂正堯や江藤淳の作品をよく読んだが、この頃、高坂や江藤を読むことはかなり勇気のいることだった。中西のこの発言からは、高坂や江藤の影響を感じ取ることはできない
中西の話を受けて、八木はこう言っている。《中西先生に触発されて、私も、もう少し若かりし頃の話を(笑)。私が、西部邁先生の『大衆への反逆』に啓発されて、バークやトクヴィルなどを手に取り、「保守思想は格好いい、なんだか新しい」と感じていたのは、ちょうど冷戦の最後のあたりでした。ソ連の凋落が著しくなると同時に、フランス革命二百年が間近に迫っていて……。》(同前)
八木は、保守思想との出会いが、小林秀雄や江藤淳、福田恆存ではなく、西部邁であることを告白しているわけだが、おそらく中西も同じようなものだろう。
西部が紹介したバークやトクヴィルなどの保守思想で、「保守」に目覚める。これが「第二世代の保守思想家」たちの特質である。つまり「亜流思想としての保守」、「イデオロギーとしての保守」である。中西や八木に「作品」がないのも当然である。
それにも関わらず、中西は保守論壇で重宝されている。何故か。それはおそらく、中西の思想的資質や才能が評価されているのではなく、「京都大学教授」だの「京都大学名誉教授」だのという肩書きが重宝されているのだろう。だからこそ、中西は、保守論壇の市民運動である「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本教育再生機構」など、色んなところに顔を出していたのだろう。■「書くことの内的必然性」の欠落
私が中西を知ったのは、彼の主著とも言うべき『大英帝国衰亡史』によってである。私はかつて、大英帝国の起源と興隆、衰退の歴史を、綿密な資料分析を通して追跡したこの本を、愛読し、熟読していた。
英国が、元々はスペインやフランスという大国の侵略に怯え、恐怖するだけの、吹けば飛ぶような小国であったこと、しかし数々の情報戦や謀略戦を勝ち抜いて、ついにスペインの無敵艦隊を打ち破り、大英帝国への道を切り開いたこと、アジアやアフリカに植民地を確保し、世界に冠たる大帝国を築き上げこと、しかし、二度の世界大戦を勝ち抜き、対独戦の勝利を祝うチャーチルの演説が、実質的には大英帝国の終わりを告げる演説であったことなどを、私は興味深く読んだ。
たとえば、最も感動的な場面であるチャーチルの対独戦勝利演説とその政治的背景について、中西はこう書いている。《それゆえ戦争が終ったとき、多くのイギリス人は自国の真の立場について理解することができなかった。
米・ソとならび、「三大国の一員」という幻想が、戦後も長くイギリス人の頭に残ることになったのは、すでに崩壊をきたしつつあった国力の現状を考えれば、とりわけ痛ましいことであった。
この点では、第二次大戦はイギリスにとって、日・独に比べはるかに深く、悲劇的な戦争だったというべきかもしれない。人間や国家の不幸の中でも、過去の幻影の中でさらに長き日々を生きつづけ、その結果、遅効性の「病魔」に悩みつづけることは、けっして小さなものではない。とりわけそのことに気づかぬまま、生気を失いつづけることは、とりわけ大きな悲劇というべきかもしれない。
四五年五月八日、チャーチルは下院で、「ドイツの無条件降伏」の報を伝え、歓呼の声を背にして、その足でバッキンガム宮殿に向い、午後五時すぎ、国王ジョージ六世夫妻、エリザベス、マーガレットの二人の王女とともに宮殿のバルコニーに現われ、大歓声のなかで対独戦の勝利を祝った。
しかしそれは、もはや「帝国最良の日」ではなかった。
チャーチルはその数週間後の総選挙に敗北し、政権の座を追われたし、大戦中のイギリス人の生活をも支えた、アメリカからの一大経済支援(それは不適切にも武器貸与法と訳されている)もストップされた。そしてイギリスは兵器よりも、食糧輸入の支払いにさえ困難をきたす状況に直面しつつあった。
帝国はすでに破産していたのである。そしてそれらの根因は、やはり、あの「一九四〇年の夏」にあった。》対独戦勝利と同時に大英帝国は崩壊していた――。なかなか感動的な、考えさせられる場面である。私はこの『大英帝国衰亡史』を、「大日本帝国衰亡史」として、あるいは近未来の「日本衰亡史」として読むことも可能であると思いつつ読んだが、果たして著者の中西に、そのような自覚はあっただろうか。
大英帝国に限らず、ローマ帝国以来、何度となく繰り返されてきた「帝国の衰退」あるいは「帝国の滅亡」というテーマが、政治学者としての中西の学問的テーマなのだろうが、そのテーマは、中西自身の「存在」の問題と深く結びついているだろうか。
中西が「国家の衰退」について論じる時、その多くは、いかにして日本という国家の衰退を防ぐか、いかにして日本を復活させ、強い国家にするか、というところに重点が置かれている。しかし、中西が書くその対処法、ないしは処方箋はズレているようにしか見えない。
もし、「帝国の衰退」あるいは「国家の衰退」というテーマが、中西自身の「存在」の問題に直結していたら、中西はもっと違った思想家、もっと違った政治学者になっていたのではないか、と私は想像する。
私が『大英帝国衰亡史』を熟読していた頃は、中西は地味な政治学者の一人にすぎず、後に保守論壇や保守系ジャーナリズムに毎月のように顔を出し、政界や政権の奥まで食い込んで、しかも内閣のブレーンにまでなるというような行動的、実践的なタイプの学者とは想像もできなかった。
そのため、中西に対する第一印象は決して悪くはなかった。一つのテーマを追い続け、深く沈潜していく政治学者のように思われたからだ。しかし、実態は違っていたようだ。
いや、私が知らなかっただけで、既にその前から保守論壇や保守系ジャーナリズムの「売れっ子評論家」だったのかも知れない。そして、『大英帝国衰亡史』もまた、その浅薄な政治論や政治家論の延長線上にある著作だったのかもしれない。
いずれにせよ、中西はその後、異例とも言える頻度で、様々な保守系オピニオン誌の常連寄稿者として、保守論壇や保守系ジャーナリズムに顔を出すようになったわけだが、私はその頃から、中西の政治論や国家論、歴史論の類にほとんど関心を持てなくなった。
何故中西の書くものは私の関心外となったのか。それはおそらく、中西の書くものに、「書くことの内的必然性」がまるで感じられなかったからだろう。
「書くことの内的必然性」ということで言うならば、江藤淳は大日本帝国の滅亡や連合艦隊の消滅について、次のように書いている。《戦前の日本で、自分が国家と無関係だと感じた子供はいない。しかし私にとっては、それはある意味では祖父がつくったもののように感じられた。父にとっては、それは自分の父親とその友人たちがつくり、かつ守ったもののように感じられたにちがいない。言葉をかえていえば、父のなかにはおそらく国家のイメイジが自分の父親の記憶と結びついて生きていたにちがいなく、私のなかではそれは祖父の肖像写真と結びついて生きていた。(中略)
しかし敗戦によって私が得たものは、正確に自然が私にあたえたものだけにすぎない。私はやはり大きなものが自分から失われて行くのを感じていた。それはもちろん祖父たちがつくった国家であり、その力の象徴だった海軍である。私は第二次大戦中の海軍士官の腐敗と醜状を自分の眼で見る機会があったから、この海軍が祖父の時代の海軍と同じものではないらしいことに漠然と気がついてはいたが、それでも連合艦隊が消滅したことは心に空洞をあけた。》(「戦後と私」)江藤淳が日本という国家を語り、論じる時、それは抽象的な国家を語り、論じているわけではない。父や祖父の思い出や肖像写真と直結したものとしての肉感的な国家を語り、論じているのだ。
江藤淳の語る国家は、「祖父たちがつくった国家」であり、その国家の力の象徴だった海軍が滅亡すれば、それは自分の肉体の一部が、あるいは肉親が滅亡するようなものだった、と言っていい。そういう自覚と「内的必然性」に基づいて、江藤淳は国家について語り、論じている。そこから江藤淳の政治論や政治家論、あるいは歴史論は始まっている。
江藤淳は、単に個人的な家族の思い出話をしているわけではない。むろん、そういう江藤淳的な国家の語り方をどう評価するかは別であるが、少なくともそれが、抽象的な国家論でないことは明らかである。(以下略)
![]() ・
・![]() (続きは、『思想家・山崎行太郎のすべて』が分かる!!!有料メールマガジン『週刊・山崎行太郎』(月500円)でお読みください。登録はコチラから→http://www.mag2.com/m/0001151310.html
(続きは、『思想家・山崎行太郎のすべて』が分かる!!!有料メールマガジン『週刊・山崎行太郎』(月500円)でお読みください。登録はコチラから→http://www.mag2.com/m/0001151310.html